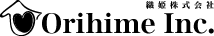【成長する充電インフラ市場】投資家必見の最新動向と有望企業を解説
 電気自動車などの充電インフラ市場は、環境への意識が高まることに伴い急成長している投資分野です。
電気自動車などの充電インフラ市場は、環境への意識が高まることに伴い急成長している投資分野です。日本政府は2030年までに現在の約3万箇所ある充電スポットを10倍に増やす計画を発表しました。
また、世界的にも中国や欧州を中心に市場の拡大が進んでいます。
しかし、急速充電器(短時間で充電できる高出力の充電設備)1基の設置には約2,500万円の高いコストがかかります。
さらに、設置するためのスペース不足や充電設備の運用効率なども普及を妨げる要因です。
本記事では、充電インフラ市場の将来性と直面している課題について、理解しやすいように解説していきます。
電気自動車の充電設備:基本情報と将来性

世界と日本での電気自動車の普及状況と充電スポットの現状
世界的には中国や欧州諸国が先行しており、中国では電気自動車(EV)の販売台数が2025年には全体の約30%を占める見込みです。欧州ではノルウェーやオランダなどが充電設備のネットワーク整備で先導的な役割を果たしていて、日本もこれらの国々に追いつく必要があります。
また、日本国内ではオリックスが2025年までに5万箇所の充電ステーション設置を目指しており、大手企業による積極的な投資も進んでいます。
素早く充電できる「急速充電」と通常の「普通充電」の違い
急速充電は直流電力(DC)を使用し、バッテリーへ直接高出力で電力を供給するため、短時間で効率的に充電できます。これに対して普通充電では、家庭用と同じ交流電力(AC)を車両に送り、車に搭載された変換器で直流に変える仕組みです。
そのため、充電にかかる時間や設備の大きさ、設置にかかる費用に影響を与えています。

急速充電器の出力は通常50キロワット〜150キロワットほどで、約30分でバッテリー容量の80%まで充電が可能になります。
一方、普通充電器は3キロワット〜6キロワット程度の出力しかないため、満充電には数時間必要です。
また、急速充電器には高性能な直流変換装置が内蔵されており、大型で価格も高くなりますが、短時間での充電を実現してくれる利点があります。
電気自動車の充電を支える最新技術とこれからの進化
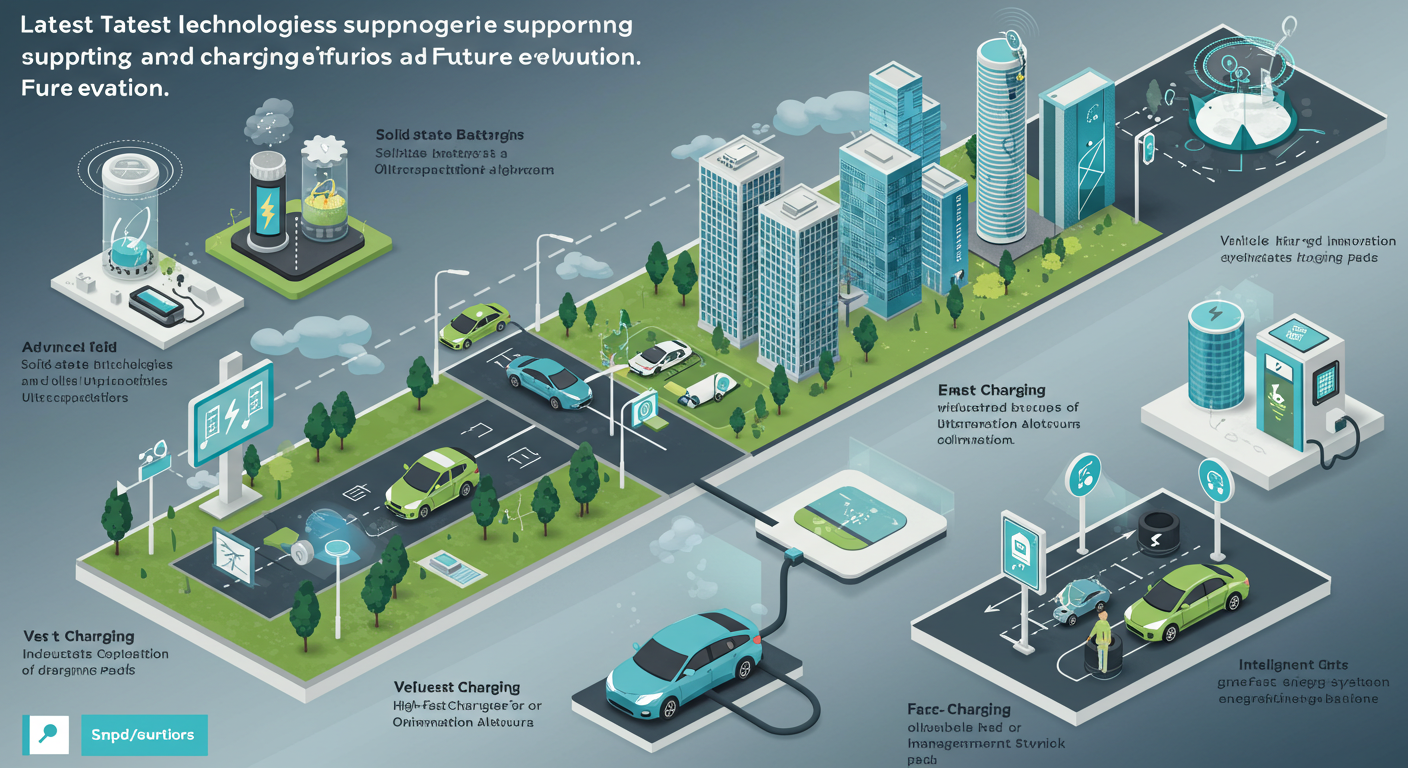
短時間充電技術の最新トレンドと将来展望
これまでの充電方式では長い時間がかかるため、使う人にとって便利さが低下していたのが現状です。しかし、速い充電技術やケーブル不要の充電システムが導入されたことで、充電にかかる時間が大幅に短くなり、使いやすさが向上しました。
Zeekrの高性能充電技術(5.5C技術と呼ばれるもの)では、バッテリー残量10%から80%までをたった10.5分で充電できるようになっています。
また、シルバラードEVは高電圧システム(800ボルト方式)を取り入れており、わずか10分の充電で約160キロメートル走行できる電力を補給することが可能になりました。
ケーブル不要の充電技術とV2G技術の可能性
ワイヤレス充電は、充電コードを接続する手間がなくなり、車を止めている時や走っている間に自動で充電できるので、使う人にとって便利になります。一方、V2G技術(車から電力網へ電気を送る仕組み)では、電気自動車のバッテリーを電力網につなげることで、蓄えた電気を供給できるようになります。
これにより、電力の需要と供給のバランス調整や、太陽光や風力などの再生可能エネルギーをより安定して使えるようになるのです。
太陽光などの再生可能エネルギーと組み合わせた新しい活用法
再生可能エネルギーと電気自動車(EV)充電インフラの組み合わせは、環境への負担を大きく減らしながら、エネルギーの効率化につながると考えられています。再生可能エネルギーは二酸化炭素(CO2)を出さないクリーンな電力源です。
これをEV充電に活用すると、石油や石炭など従来の燃料に頼る発電方式と比べて、環境への影響を抑えることができます。
さらに、太陽光発電のような仕組みでは、地域内で作って使う「地産地消」が可能なため、長距離の送電で失われるエネルギーも減らせる利点があります。
日本で初めて導入された「グリーン充電」では、施設に直接発電設備がなくても、100%再生可能エネルギー由来の電力でEVを充電できる仕組みが整っています。
充電設備市場を後押しするお金の流れ

大手投資家たちによる充電設備への投資傾向
環境問題への対応と市場の成長可能性の高さから、多くの大手投資家や企業がこの分野に注目しています。とりわけ投資意欲を高めているのは、各国政府の支援策や補助金制度です。
日本では、2030年までに公共の場所で使える高速充電器3万基を含む合計30万基の設置を目標としています。
アメリカでも同様に、2024年には政府が約623百万ドル(約900億円)を充電設備に割り当てるなど、政策面からの後押しが目立ちます。
具体的な例として挙げられるのが、テラチャージ株式会社の取り組みです。
同社はシリーズDと呼ばれる大規模な資金調達で合計100億円を集め、日本国内外で充電設備の拡充を進めています。
これにより、一般家庭用から商業施設まで幅広い充電サービスの提供が可能です。
充電設備を広げる上での問題点と解決方法
充電設備の普及を妨げる主な問題としては、以下の要因が考えられます。- 設置コスト
- スペース不足
- 運用効率
- 老朽化
それらの課題を解決するためには、政府と民間企業が協力して補助金制度の充実や、新しい技術の開発、そして地域の特徴に合わせた設置計画が大切です。
しかし、最も大きな壁となっているのは、設置費用の高さです。
急速充電器1台を設置するには約2,500万円もの費用がかかり、維持管理にも年間約250万円が必要となっています。
また、都市部では土地の確保が難しく、充電器を設置する適切な場所を見つけることに苦労しています。
反対に、地方では利用する人が少ないため、採算が取れないという問題です。
急速充電器国内販売台数トップクラスの東光高岳の成長性
 東光高岳が成長し続けている背景には、「SERA」シリーズの急速充電器を中心とした多様な製品ラインアップがあります。
東光高岳が成長し続けている背景には、「SERA」シリーズの急速充電器を中心とした多様な製品ラインアップがあります。また、次世代技術への積極的な投資や、2050年までに温室効果ガスの排出と吸収をバランスさせるカーボンニュートラル目標に向けた社会的需要も追い風となっています。
東光高岳は2009年に初めての充電器を販売して以来、国内で約5,000基を設置してきました。
さらに、日本発の充電規格である最大出力150kWの「HFR1-150B12」モデルや、1ヶ所で最大350kWの電力を供給できる次世代超急速充電器など、先進的な製品開発にも力を入れています。
これらの製品は国内外の電気自動車に対応し、使いやすさと高い効率性を実現しました。
加えて、全国に整備された保守・点検のサポート体制も東光高岳の強みです。
この充実したアフターサービスによって、顧客からの信頼を獲得し、長期的な関係構築に成功しています。
まとめ
電気自動車の充電設備市場は急速に成長しており、環境問題への対応と市場拡大により投資価値が高まっています。この成長を裏付けるのは、日本政府が2030年までに充電スポットを現在の約3万箇所から10倍に増やす計画を発表したことです。
今後は急速充電技術やワイヤレス充電、V2G技術(車から電力網へ電気を供給できる仕組み)など技術の普及により、充電の使いやすさと効率が向上するでしょう。
このような成長市場の動向をいち早く察知し、投資チャンスを掴むには、市場を読み解く確かな眼が必要です。
EVや充電インフラ関連銘柄を含む、これから爆上がりする可能性のある銘柄の見極め方を学びませんか?
期間限定・人数限定の特別講座ですので、今すぐ下のリンクから登録して、勝ち組投資家への第一歩を踏み出しましょう。
詳しくはこちらから→▶ 無料動画講座を視聴する