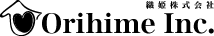円高/円安による企業業績への影響:業種別分析と投資戦略を解説
 円高・円安とは、日本円が外国のお金(ドルやユーロなど)に対して価値が上がったり下がったりする現象です。
円高・円安とは、日本円が外国のお金(ドルやユーロなど)に対して価値が上がったり下がったりする現象です。日本では、日本と米国の利子率の差が広がっていることや、アメリカの中央銀行(FRB)が利子率を引き上げたことにより、円の価値が下がる「円安」の状態が続いています。
この状況は海外に製品を売り出している製造業にとっては良い影響がある一方で、外国から物を多く輸入している産業や私たち消費者の生活費増加という問題も引き起こしています。
本記事では、お金の価値変化が業種にどのような影響を与えるか、投資をされる方々が資金運用戦略の参考になるよう解説いたします。
円高・円安の基本:仕組みと日本の現状

円高・円安とは?為替レートが変動するメカニズム
円高とは円の価値が外国通貨よりも高くなる状態です。一方、円安はその逆で円の価値が外国の通貨と比べて低くなっている状況を表しています。
通貨の交換比率(為替レート)の変化は、お金の取引市場(外国為替市場)で円がどれだけ求められているか、あるいは売られているか需要と供給のバランスによって決定されるのです。
為替レートが動く原因には以下の要因があります。
- 国を越えた経済活動や各国の金融政策
- 輸出入のバランス(貿易収支)
- 国ごとの金利の違い
たとえば、日本からの輸出が増えると、海外の企業が日本円を購入する必要性が高まり、円の価値が上昇して円高になりやすいです。
逆に、日本が海外から多くの商品を輸入する場合は、円を外国通貨に換える動きが強まることから、円の価値が下がって円安になります。
日本の円安傾向はなぜ起きている?日米金利差と市場要因
2022年以降、アメリカ連邦準備制度理事会(FRB)は物価上昇(インフレ)を抑えるため、急速に中央銀行が決める基準となる金利を引き上げていきました。その一方で、日本銀行(日銀)はお金を借りる際の金利を低く保つ政策を続けたため、日米間で大きな金利の差が生じることになったのです。
このような金利の開きにより、投資家は利益を得られるドル建ての資産へとお金を移す動きが加速し、円の価値が下がる現象(円安)を引き起こしました。
具体的には、日米の実質的な金利の差(10年満期の国の借金である国債の金利)と円とドルの交換レートには強い関連性があります。
2021年7月以降、この関連の強さを示す指標は0.94という非常に高い数値となり、両者が密接につながっていることが明らかになりました。
円安で優位に立つ企業・業種
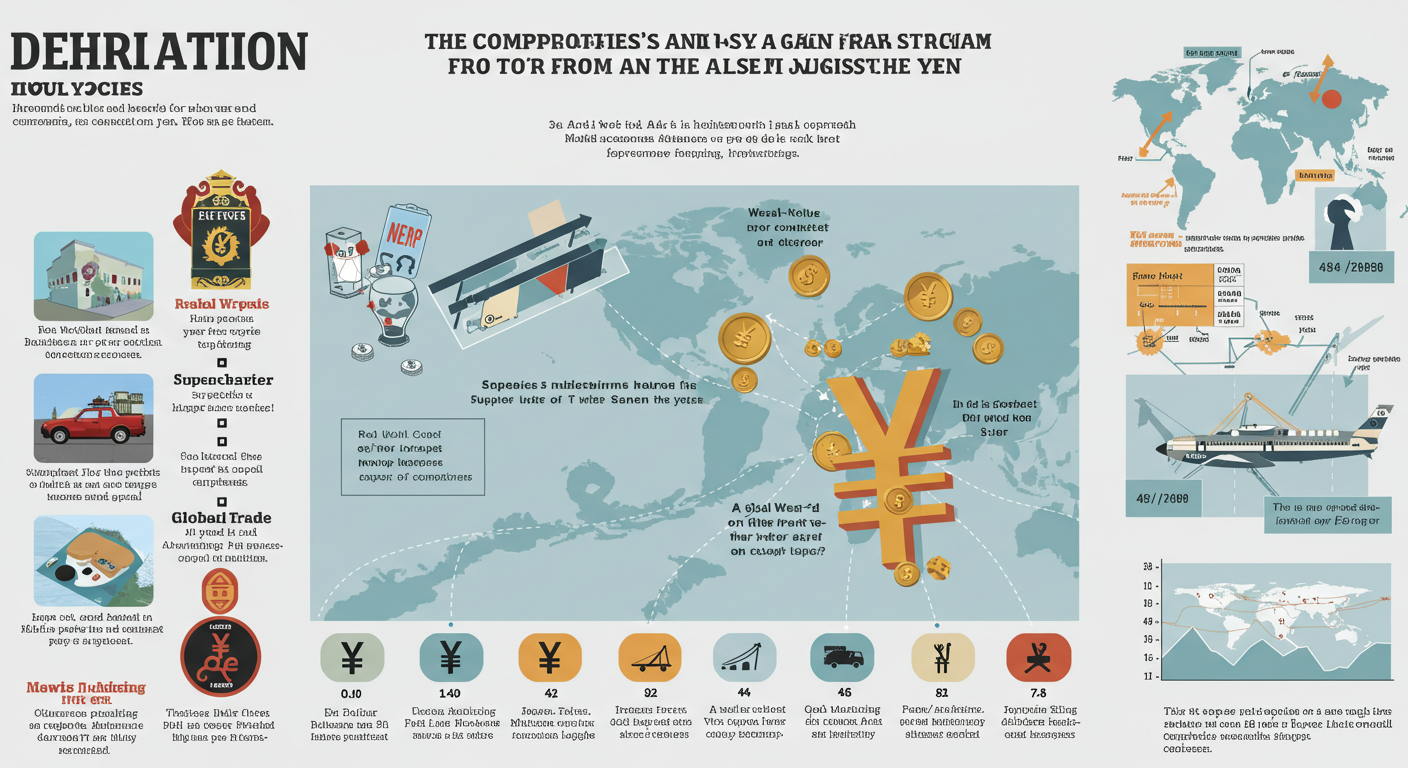
輸出型製造業(自動車、電機、精密機器など)
自動車、電機、精密機器といった輸出型製造業は海外売上比率が高く、円安による為替差益や価格競争力の向上を通じて業績を伸ばす傾向にあります。自動車業界ではトヨタ自動車が1ドルあたり1円の円安で年間450億円の営業利益増加が見込まれています。
また、電子部品メーカーの日本電産や村田製作所も、円安と電気自動車(EV)需要の高まりを背景に過去最高の業績を達成しました。
2024年度第1四半期には、自動車メーカー各社が円安による利益増加を報告しています。
- トヨタ自動車は3700億円
- ホンダは475億円
- マツダは439億円
また、日本電産は2022年度に会社全体の売上(連結売上高)が前年比18.5%増加し、営業利益も7.2%上昇したのです。
この背景には、中国やアメリカ市場での好調な販売と円安効果があるといえるでしょう。
インバウンド関連ビジネスへの好影響
円安によって日本円の価値が下がると、外国人観光客にとって日本旅行が割安になります。このため、日本国内での買い物や食事などの消費活動が活発になり、観光地やお店の売上アップにつながるでしょう。
また、円安は日本を訪れる外国人の数を増やすだけでなく、一人一人が使うお金の量も多くする効果があります。
海外からのお客様にとっては、日本での生活費や旅行にかかるお金が他の国と比べて安く感じられるので、旅行先として日本の魅力が高まるのです。
円高で優位に立つ企業・業種
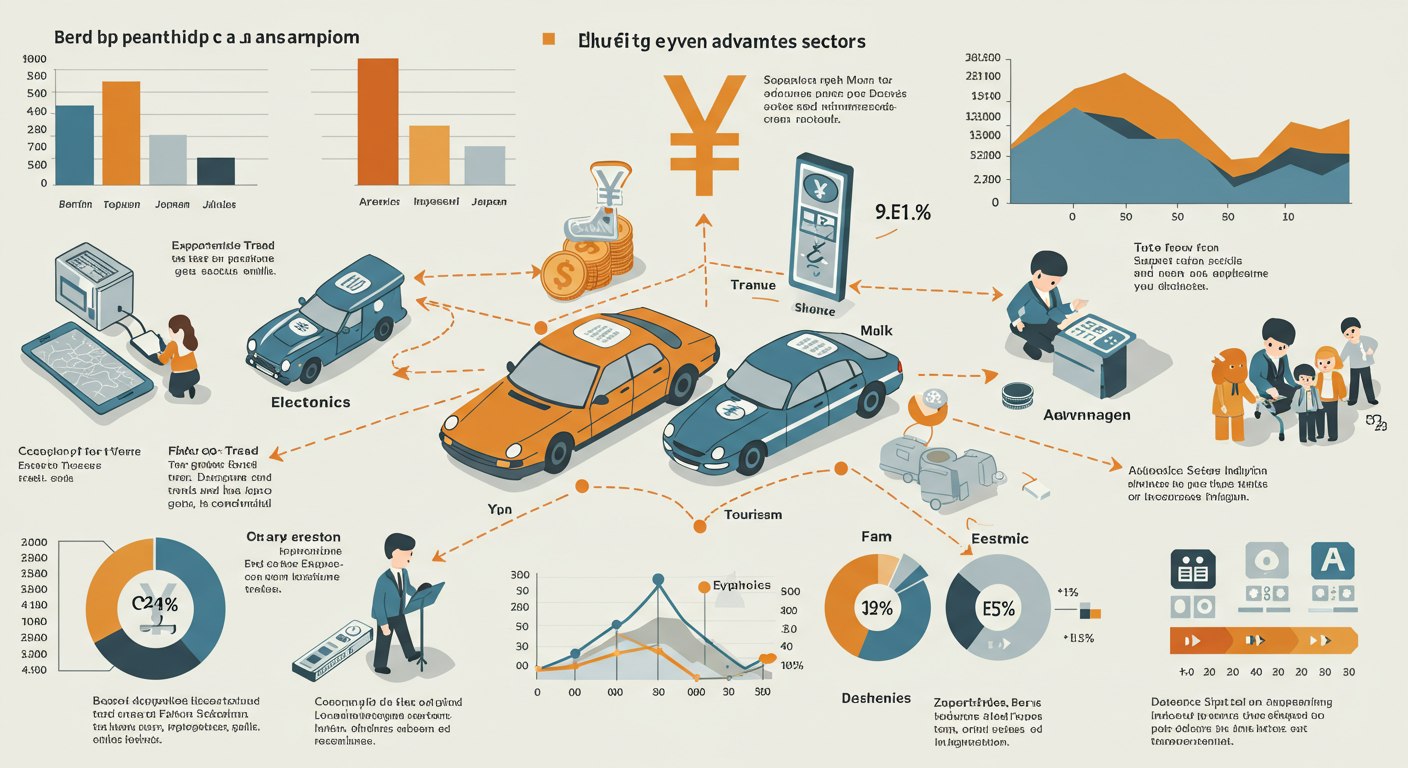
輸入依存度の高い企業(エネルギー、食品、原材料など)
円高(日本円の価値が外国通貨より高くなること)が進むと、同じ金額の日本円でより多くの海外製品や原材料が買えるようになるため、輸入にかかる費用が減少します。このコストダウンは、海外からの輸入に頼っている業界にメリットとなり、会社の業績向上につながりやすいです。
エネルギー分野では原油や天然ガスといった燃料をアメリカドルで価格設定(ドル建て)して購入することが多いです。
円高の状況では、これらの燃料代が日本円に換算したときに安くなるため、電気を作る費用や物を運ぶコストを下げられます。
食品業界も同様で、小麦や大豆など材料の多くを外国から取り寄せていますから、円高によって原料の買い付け価格が下がると、製品を作る費用を大幅に抑えることが可能です。
円高環境でも恩恵を受ける小売業
円高になると、同じ金額の日本円でより多くの外国製品を買えるようになり、輸入商品の仕入れ価格が下がります。このため、企業はコストを減らしやすくなるでしょう。
また、消費者にとっては海外からの輸入品が安くなることで買い物意欲が高まり、売上数量の増加も見込まれています。
最近の円安傾向が日本経済全体に与える影響
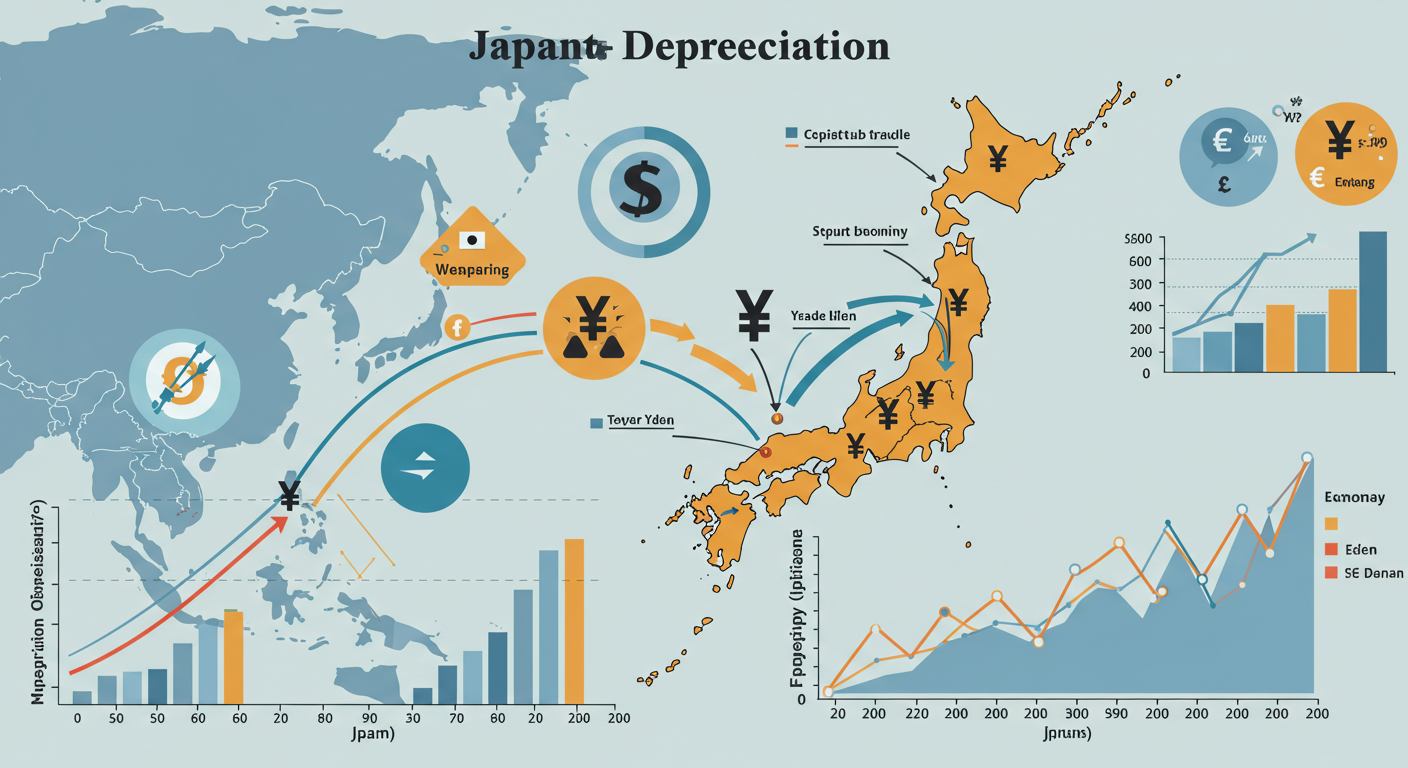
輸入コスト増加による物価上昇と消費者負担
日本は多くのエネルギー資源や食料品、工業製品の材料を海外からの輸入に頼っています。そのため、「円安」が進むと、輸入品の価格が上昇し、私たちの日常生活にも影響が出やすいです。
海外から買う商品の値段が高くなり、それが国内の商品価格にも反映されていきます。
例えば、スーパーでの食品や日用品の値段が上がることで、家計の負担が増えてしまい、 消費者はお金を節約する傾向が強まるでしょう。
また、ガソリン代や電気・ガス料金といった毎日の生活に欠かせないエネルギー関連の費用も増加します。
これらは基本的な生活費として避けられないため、家計への負担はさらに大きくなります。
企業の海外生産シフトと国内雇用への影響
企業が海外で生産拠点を設ける主な理由は、為替(通貨の価値変動)によるリスクを避けることや現地の市場ニーズにより素早く対応するためです。そのため、円安だけでは、これらの海外展開戦略が見直されることはあまりありません。
加えて、日本国内の労働者一人当たりの生産効率の低さや雇用制度の柔軟性の欠如も、企業が国内での生産に戻ることを難しくしている要素となっています。
具体例として、トヨタ自動車の事例が挙げられます。
トヨタ自動車は円の価値が下がっても、海外からの輸入に頼るよりも現地での生産を大切にしています。
トヨタは為替の変動がもたらす予測の難しさや、国と国との間の貿易上の対立(通商摩擦)を避けるため、北米などの市場で現地生産を積極的に増やしてきました。
まとめ
円高・円安が日本企業の業績に与える影響は業種によって異なります。円安は輸出型製造業やインバウンド関連ビジネスに有利に働く一方、円高は輸入依存度の高い企業や小売業に恩恵をもたらします。
今後も日米金利差による円相場の変動が続く見通しの中、投資家は こうした為替変動と企業業績の関係を見極める目を持つことが重要です。
相場のプロである北川博文氏の「超実践投資講座」では、為替変動を含む様々な市場要因を分析し、未来の株価が書いてある場所を見つける方法を学ぶことができます。
初心者からベテランまで、勝ち組投資家になるためのノウハウを無料の動画講座で手に入れてみませんか?
たった3秒のメール登録で、90%以上の確率で株価が上がるパターンなど、すぐに役立つ投資情報が手に入ります。
期間限定・人数限定の特別公開ですので、この機会をお見逃しなく!
詳しくはこちらから。→▶ 無料動画講座を視聴する