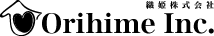景気後退に強いディフェンシブ銘柄|特徴と選び方を詳しく解説
 ディフェンシブ銘柄とは、景気の良し悪しに関わらず比較的安定した業績を維持できる企業の株式です。食料品や医薬品、公共インフラなどがディフェンシブ銘柄に該当します。
ディフェンシブ銘柄とは、景気の良し悪しに関わらず比較的安定した業績を維持できる企業の株式です。食料品や医薬品、公共インフラなどがディフェンシブ銘柄に該当します。ディフェンシブ銘柄が注目される理由は、提供している製品やサービスが日常生活に欠かせないからです。
実際、1990年以降に発生した4回の景気後退期において、消費財とヘルスケア分野のみがプラスの運用成績を記録しました。
この事実からも、経済全体が苦しい時期でもディフェンシブ銘柄の強さが証明されています。
本記事では、投資家向けに、ディフェンシブ銘柄の特徴と効果的な選び方について解説していますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
ディフェンシブ銘柄とは?景気後退に強い理由
 ディフェンシブ銘柄では、企業が提供する製品やサービスが人々の日常生活に欠かせないため、経済が落ち込む時期でも業績が比較的安定しています
ディフェンシブ銘柄では、企業が提供する製品やサービスが人々の日常生活に欠かせないため、経済が落ち込む時期でも業績が比較的安定しています具体例としては、以下の生活インフラサービスなどが該当します。
- 食料品
- 医薬品
- 電気・ガス
こうした企業は景気悪化時にも売上高が減ることが少なく、資金の流れ(キャッシュフロー)が安定している傾向があります。
そのため、経済が後退する時期には資産を守る観点から、このような景気の変動に左右されにくい株式への投資が注目を集めているのです。
ディフェンシブ銘柄の代表的なセクター
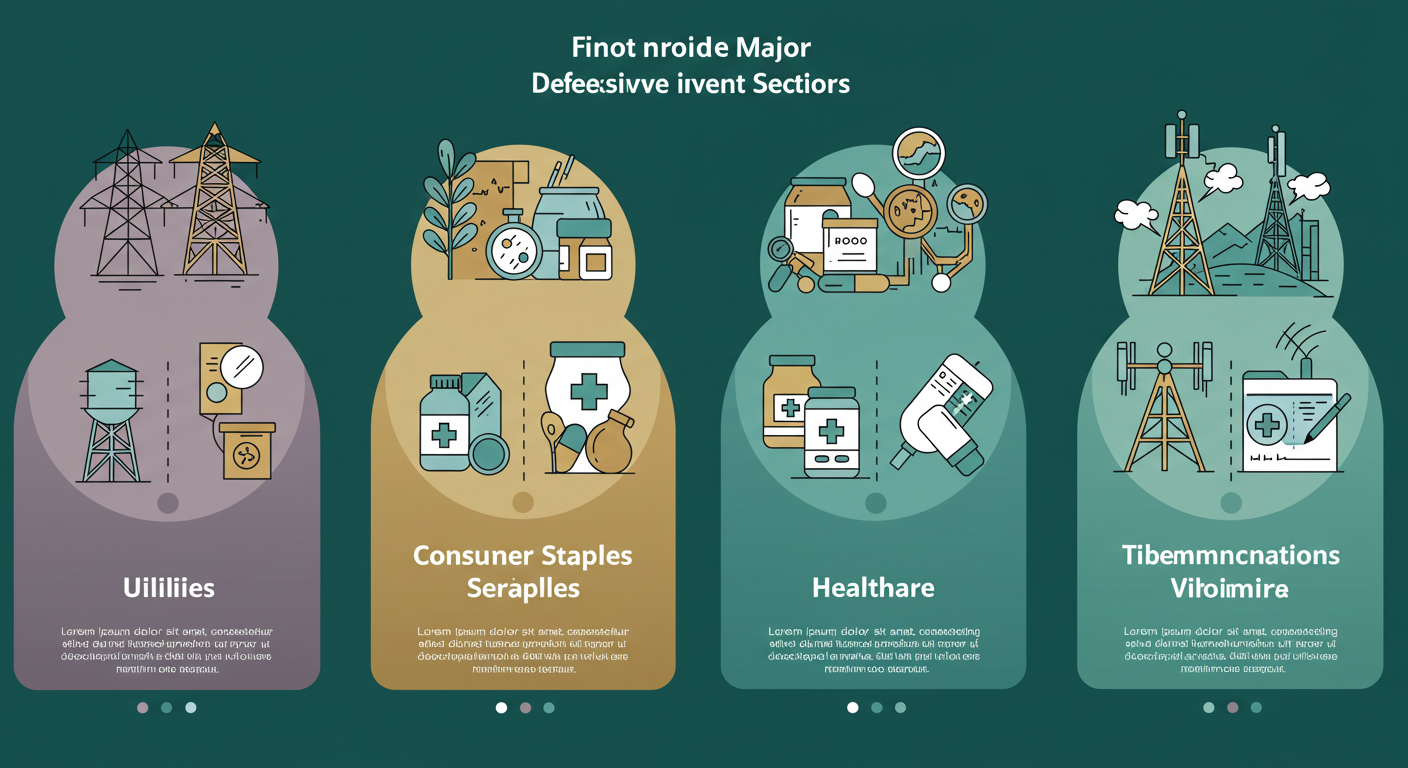
景気に左右されず安定した消費がある生活必需品セクター
生活必需品セクターは、景気の上下にかかわらず安定しています。食料品や医薬品、電力・ガスといった日常生活に欠かせないサービスへの需要は常に存在するため、企業の収益も比較的安定しているのが特徴です。
2024年の経済低迷期においても、日本ハムや東京ガスの売上高は前年と比較してわずか2〜3%の減少にとどまりました。
また、株主への利益還元である配当利回りも3%台を維持することができています。
このような安定した特性から、年金基金などの機関投資家は投資全体の約15〜20%を生活必需品セクターに配分しています。
高齢化社会により長期的に期待できる医薬品・ヘルスケアセクター
日本では2050年までに総人口の38%が65歳以上になると予測されています。これにより、長期的な治療が必要な病気や介護サービスへの需要が今後さらに拡大していくでしょう。
経済産業省の調査によれば、国内のヘルスケア市場は2025年に33兆円規模に成長する見通しです。
その中でも健康管理や医療にデジタル技術を活用するデジタルヘルス分野は、2030年までに全体の約13.5兆円を占めると予想されています。
2024年には、マイナンバーカードと健康保険証を一体化したマイナ保険証の利用が義務化されています。
これらの制度変更により、自宅などからインターネットを通じて診療を受ける遠隔診療や、人工知能(AI)を使って一人ひとりに合わせた医療サービスの提供が進んでいます。
規制産業で安定した収益構造を持つ公共インフラセクター
公共インフラ部門では、上下水道や道路整備などの事業が自治体や国と長期にわたる契約に基づいて行われています。このような構造により、景気の変動による影響を受けにくいです。
国土交通省の調査によると、インフラの老朽化対策にかかる費用は2040年代までに年間約10兆円に達する見込みです。
このため、問題が発生する前に対策を行う「予防保全型」のメンテナンス市場が今後拡大していくでしょう。
全体として公共インフラ部門は、政策によって生み出される需要と、規制によって新規参入が難しい環境が組み合わさり、景気変動に強い安定した特性を持っていると言えます。
日本市場における注目のディフェンシブ銘柄

医薬品セクターの代表格:「武田薬品工業」
結論から言うと、武田薬品工業などの医薬製品は景気の良し悪しに影響されにくい特徴があります。武田薬品工業の安定性を裏付ける具体例として、主力商品である「エンティビオ」の実績が挙げられます。
エンティビオは腸に炎症が起きる病気(潰瘍性大腸炎)の治療薬で、北米市場では前年と比べて18%も売上が増加しました。
現在では会社全体の収益の約3割をこの一つの薬品だけで支えています。
株価も2025年4月の時点では過去3年間の平均と比較して35%上昇しており、配当利回りも3.2%と、株主への還元と安定した収益性の両方を実現しています。
食品セクターの代表銘柄:「日本ハム」
日本ハムは「ディフェンシブ銘柄」として知られており、日常生活に欠かせない食品を多く扱っているため、経済情勢が変化しても安定した業績を維持しています。主力商品であるハム・ソーセージは、毎日の食卓で必要とされる商品であるため、不景気になっても売上が大きく落ち込みにくいです。
財務面では安定したキャッシュフロー(事業から生み出される現金)があります。
2024年度の統合報告書では、経常利益率(売上に対する利益の割合)が業界平均より2.3ポイント高い6.8%を達成しています。
不況やインフレ環境でのディフェンシブ銘柄のパフォーマンス
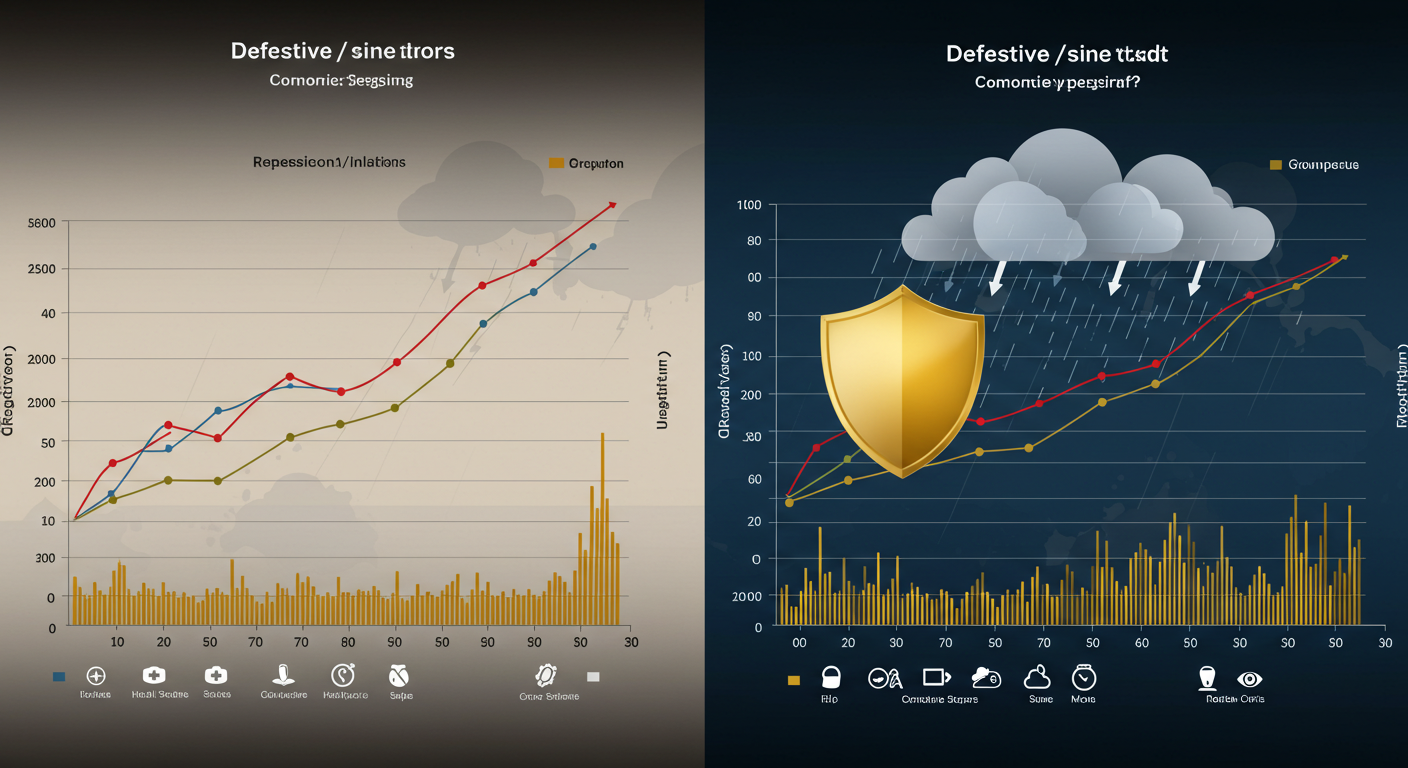 不況やインフレのような経済環境が悪化する時には、景気に左右されにくい「ディフェンシブ銘柄」が市場全体よりも良い成績を示しやすいです。
不況やインフレのような経済環境が悪化する時には、景気に左右されにくい「ディフェンシブ銘柄」が市場全体よりも良い成績を示しやすいです。日常生活に必要な製品やインフラを提供する業種は、景気が悪くなっても需要があまり減少しません。
1990年以降に発生した4回の景気後退期において、S&P500指数の中で消費財と医療関連(ヘルスケア)の分野だけがプラスの収益を記録しました。
また、これらの企業は値上げを顧客に転嫁できるため、物価が上昇する環境でも利益を守ることが可能です。
ディフェンシブ投資は老後資金運用者に適している
 ディフェンシブ銘柄は、老後資金の運用において戦略的な選択肢となります。
ディフェンシブ銘柄は、老後資金の運用において戦略的な選択肢となります。その理由は、景気の良し悪しに左右されにくい業種が資金の安定性を支え、継続的な配当収入を期待できるからです。
公益事業や医薬品分野は、経済が停滞している時期でも日常生活に欠かせないサービスや製品の需要が続くため、投資した資産が大きく減るリスクを抑えられます。
とりわけ日本では高齢化社会が進み、医療費や光熱費といった必ず支払わなければならない費用が増える傾向にあるため、これらに関連する企業の業績基盤は強まっています。
老後資金の運用では元本を守りながらゆっくりと資産を増やすことが求められますので、このような特徴はまさに適していると言えるでしょう。
まとめ
今回は、景気後退に強いディフェンシブ銘柄について解説しました。ディフェンシブ銘柄とは、私たちの日常生活に欠かせない製品やサービスを提供する企業の株式です。
具体的には、以下の関連企業になります
- 食品や日用品などの生活必需品
- 医薬品
- 電気・ガス・水道などの公共インフラ
これらの企業は、景気が悪化した時期でも比較的安定した業績と配当を維持しやすいです。
現在の日本では社会の高齢化が進み、医療技術も日々進歩していることから、医薬品やヘルスケア関連の企業は、今後も長期的な成長が見込まれていくことでしょう。
しかし、数ある銘柄の中から本当に将来性があり安定したリターンを生み出す銘柄を見極めるには、プロの目が必要です。
投資のプロである北川博文氏の「未来の株価が書かれている場所を見つける方法」を学んでみませんか?
初心者でも実践できる投資術を、期間・人数限定の無料セミナーで公開中です。
たった3秒の簡単登録で、投資成功への第一歩を踏み出しましょう。
詳しくはこちらから→▶ 無料動画講座を視聴する