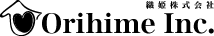企業の自社株買いが加速! 投資判断に役立つ基礎知識を解説
 自社株買いとは、企業が市場で自社の株式を買い戻すことです。
自社株買いとは、企業が市場で自社の株式を買い戻すことです。これにより、株主の皆さんの持つ株の価値を高め、1株あたりの利益を増やすことができます。
最近では、東京証券取引所(東証)が新しい方針を打ち出したことを受け、多くの企業が資金の効率的な使い方として自社株買いを増やしています。
本記事では、投資を始めたばかりの方にも分かりやすく、自社株買いの仕組みとそれがもたらす効果について説明していきます。
自社株買いとは?基本から学ぶ目的と仕組み

会社が自社の株を市場から買い戻す仕組み
自社株買いでは、株主に間接的に利益を還元しながら、同時に1株当たりの価値を高める経営戦略となります。企業がこの方法を選ぶのは、市場に出回っている株式の数(発行済み株式数)を減らすことで株主にとっての価値を向上させられるからです。
また、自社の株価が「実際の価値より安い」と判断した場合には、経営陣が自社の将来性に自信を持っているというメッセージを投資家に伝えることができます。
買い戻した株を消すとどうなる?株の総数への影響
企業が自社株を買い戻して消却すると、市場に出回っている株式総数が減少することで、財務指標が良くなり株価が上昇する好循環が生まれます。ある会社の発行済株式数が100万株から90万株へと10%減少した場合、会社の利益が10億円だとすると、1株当たりの利益は100円から約111円へと11%上昇することになります。
三菱UFJフィナンシャル・グループの事例を見てみましょう。
同グループは2023年度に300億円規模の自社株消却を行いました。
その結果、1株当たりの利益が15%も改善され、実施後半年間で株価が22%も上昇するという成果につながったのです。
多くの会社が自社株買いを増やしている理由

東京証券取引所の新しい方針と会社への影響
多くの会社が、自社株買いを増やしている要因として、2023年4月に東証が発表した「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の要請」があります。この要請は、上場企業に対して資本を効率的に活用する経営を求めるもので、多くの企業がROEやPBRなど財務指標の改善に力を入れるきっかけとなりました。
従来の日本企業は売上や利益といった経営が中心でしたが、東証の要請を機に、貸借対照表を意識した経営へと移行する企業が増えています。
株価を支える効果とお金の使い方の効率化
発行済株式数(市場に出回っている会社の株の総数)を減らすことで1株当たりの利益が増加し、株主への還元効果が見た目上も良くなります。例として、ホンダが2024年に行った1兆1000億円規模の自社株買いは、翌日の株価が12%も急騰する結果をもたらしました。
資金の使い方として見ると、低金利環境では余った資金の運用方法としての魅力が高まっています。
そのため、内部に貯めたお金(内部留保)が増えた企業が、新しい設備への投資や他社の買収ではなく、自社株買いを選択するケースが増えているのです。
円の価値が下がることと外国の投資家の動き
日本銀行が発表した(資金循環統計)によると、2024年度には海外の投資家による日本株の売却額が10兆円を超えました。これは過去5年間で最大の資金流出規模となっています。
とりわけ半導体関連の企業や銀行・証券などの金融関連企業の株式で著しい売りの動きが見られました。
また、東証株価指数(TOPIX)を構成する銘柄の約4割で、海外の投資家が保有する株式の割合が3%以上も減少しています。
そのため、企業が自社の株式を市場から買い戻す「自社株買い」による流通株式数の調整が株価安定化にもたらす効果が見直されています。
自社株買いで会社の数字と株価はどう変わる?

自己資本利益率(ROE)が良くなる仕組み
ROEは「株主資本利益率」とも呼ばれ、「当期純利益÷自己資本×100」という計算式で求められます。
この指標は、会社が株主から預かった資金をどれだけ効率的に利益に変えているかを示しや数値です。
自己資本(分母)が減少すると、計算上ROEは上昇することになります。
これが自社株買いがROEを改善させる仕組みです。
ROEの数値が良くなると、投資家からは「資金を効率的に活用している企業」として高く評価されるため、株価の適正な評価につながっていきます。
実際に東証一部上場企業を分析したデータでは、自社株買いを実施した企業のROEは平均で0.8%ポイント上昇した結果が出ています。
1株あたりの利益(EPS)が増えて株価が上がる効果
自社株買いによって、市場に出回っている株式の数(発行済み株式数)が減少します。その結果、企業の純利益(税引き後の利益)を分配する対象が少なくなるため、1株あたりの利益EPSが向上する仕組みです。
EPSが増加すると、投資家からは「企業の収益性が高まった」と評価され最終的に株価の上昇につながる可能性があります。
日本企業の中で大規模な自社株買いを実施した企業では、その発表直後に株価が急上昇したケースがあります。
株価が急上昇した要因は以下によるものです。
- EPSの向上
- 市場での株式の需要と供給のバランスが改善されたこと
さらに、自己資本に対する利益の割合を示すROE(自己資本利益率)も同時に改善されることが多く、「企業が資本を効率的に活用している」という投資家の期待感を高める効果もあります。
株価と会社の資産価値の比率(PBR)が改善し投資家の評価が変わる
自社株買いは、企業の株価純資産倍率(PBR)を改善し、投資家からの評価を高める効果があります。これにより、企業は市場での存在感を強め、株式の価値向上が期待できるでしょう。
PBRとは「株価÷1株あたりの純資産」で計算される財務指標です。
自社株買いを行うと純資産が減少し、同時に株価が上昇する場合、PBRの数値は良くなります。
また、発行済み株式数が減ることで1株あたりの利益(EPS)が向上したり、自己資本利益率(ROE)が改善されたりすることも、投資家から高い評価を得る要因です。
ただし、株価が変わらない場合や自社株買いの規模が小さいときは、効果が限られてしまうため注意が必要になります。
まとめ
企業の自社株買いは、投資を判断する際の重要な指標として注目を集めています。自社株買いとは、企業が市場から自社の株式を買い戻す行為のことです。
自社株買いには様々なメリットがあり、発行済株式数が減少することで以下の財務指標が改善されます。
- 株主資本利益率(ROE)
- 1株当たり利益(EPS)
- 株価純資産倍率(PBR)
これにより、株主にとっての価値が高まり、株価上昇にもつながります。
東京証券取引所が資本効率を重視する方針を打ち出していることから、今後も企業のバランスシート(資産と負債のバランス)経営へのシフトと自社株買いの拡大が予想されています。
投資家にとっても、企業の自社株買いの動向は重要な投資判断材料となるでしょう。
しかし、多くの個人投資家はこうした企業の動向を見極め、次に上昇する銘柄を見つけることに苦労しています。
「未来の株価が書いてある場所」を知っていれば、こうした予測も可能になります。
実際に日経平均4万円相場を的中させた北川博文氏の「北川流投資術」では、独自の投資手法を学ぶことができます。
今なら無料の動画講座を期間限定・人数限定で公開中です。
たった3秒メールアドレスを登録するだけで、すぐに役立つ投資情報を手に入れることができます。
詳しくはこちらから→▶ 無料動画講座を視聴する